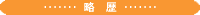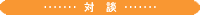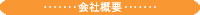月刊経営情報雑誌「マスターズ(MASTERS)」(国際通信社)、「アンカー(ANCHOR)」(報道通信社)、「センチュリー(CENTURY)」(USPマネジメント)対談取材記事掲載の経営者が参加する国際通信社グループ運営の異業種ネット
農事組合法人 栗駒高原 対談取材記事
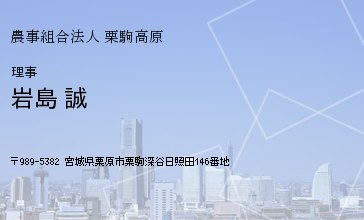


愛情を込めて鶏を育て
美味しいたまごをつくる
農事組合法人 栗駒高原
理事 岩島 誠
「鶏1羽1羽に愛情を込めて、美味しいたまごをつくっています」

養鶏業一筋に歩み続けてきた岩島理事。かつては100万羽もの鶏を“ケージ飼い”していたが、今は飼う鶏の数を大きく減らし、“平飼い”にこだわり、手間暇掛けて1羽1羽を丁寧に飼育することに情熱を注いでいる。
一般的に効率が悪いと言われる“平飼い”であるが、理事がそれにあえてこだわる理由は、たまごをつくり続けてくれる鶏を想う心にあった。
「鶏には自然を満喫させてあげたいんです」。
きっと、長く鶏と時間を共にする中で動物への愛情が育まれていったのだろう。
そうして自由気ままに育った鶏が、美味しいたまごをつくれるのだ。
理事はこれからも、あくまで鶏に主眼を置いた養鶏業を続けていく。
自由な環境で伸び伸びと育った鶏がつくる有精卵が自慢の『栗駒高原』。同所を営む岩島理事は、長年養鶏業を続けてきたベテランだ。本日はそんな理事のもとを、俳優の村野武範氏が訪問。苦難を乗り越え、鶏のことを考えた丁寧な飼育で、美味しいたまごづくりに挑み続ける理事の横顔に迫った。
先の大震災を転機に
鶏の“平飼い”に着手する
村野 『栗駒高原』さんでは、たまごをつくっていらっしゃるそうですね。
岩島 ええ。私の祖父と父が埼玉県三郷市ではじめました。立ち上げ当初は東京に納めるのに立地的に良かったので、取引先から重宝されましてね。しばらくして規模を拡大することになり、1973年からは宮城県栗原市で養鶏業を手掛けるようになりました。当時は業界でも上位に入る数の鶏を飼育していたんですよ。餌やりなどもほとんどがオートメーションされた棟を幾つも所有していて、1棟あたり2万~3万羽、合計約100万羽もの鶏を飼育していました。
村野 では、岩島理事はかねてから後継を意識されていたのですか。
岩島 住まいが職場、というような環境でしたので、自然と養鶏業を継ぐという意識が芽生えていきましたね。ただ、学業修了後すぐに家業には入らず、お世話になっていた鶏の餌をつくる会社の研究所で鶏の基礎的な知識を教わり、しばらくして家業に戻りました。そうして父と力を合わせて養鶏場を続けていたのですが、経営があまり芳しくない状況に陥ってしまいましてね……。2006年に事業譲渡することになったんです。
村野 なんと……。お父様としても理事としても、断腸の思いの決断だったことでしょう。
岩島 そうですね。厳しい状況ではありましたが、幸いにもこちらの農場は手もとに残すことができたので、養鶏業に再挑戦することができました。ところが、先の大震災が起こりましてね。大きな被害こそなかったものの、たくさんの方々の人生が一変するのを目の当たりにしました。そうした中で、私も一度は養鶏業から離れることになったのですが、紆余曲折を経て再び養鶏業に戻ってきた次第です。現在は、以前手掛けていた“ケージ飼い”ではなく、“平飼い”という飼育方法で鶏を育てていて、メスを約300羽、オスを18羽飼育しています。
たまごづくりに懸ける想いを
消費者に伝えたい
村野 数々の受難を乗り越えて、再び養鶏業に戻ってこられたのは素晴らしいことだと思います。ちなみに、新たにはじめられた“平飼い”とはどういった飼育方法なのでしょう。

▲岩島理事の説明に真剣に耳を傾ける村野氏
岩島 ケージなどに鶏を入れて飼育するのではなく、鶏が自由に地面の上を歩き回れるようにした飼い方のことを指します。以前手掛けていた“ケージ飼い”に比べて、何かと手間暇が掛かる方法ではあるのですが、私はあえてそれにこだわっているんですよ。
村野 なぜその飼育方法にこだわっていらっしゃるのですか。
岩島 鶏にもっと伸び伸びと過ごしてもらいたかったからです。と言いますのも、長く時間を共にする中で愛着のような想いが湧いていきましてね。“ケージ飼い”では鶏も窮屈で大変だろうと思うようになり、1羽1羽を丁寧に育てられる“平飼い”に着手しました。また、自分の行動に対する鶏のリアクションを観察することに楽しさを見出したのも“平飼い”にこだわる理由ですね。ですから、今は鶏に関わる作業のほとんどを手作業で行っているんですよ。昔は餌を与えるのも機械で管理していましたが、餌をつくることも与えるタイミングも、全て自分の裁量で行っています。餌を与えた時に、食べてくれている姿を見るのが何よりの楽しみです。
村野 お話からは、愛情を込めて鶏を育てていらっしゃることが窺えます。しかし、動物を相手にする仕事ですし、加えて自分の感覚が頼りになるだけに、難しい側面もあるのではないですか。
岩島 おっしゃる通りです。餌が美味しくできていなければ、鶏も喜んでくれません。そこが難しいところではありますが、努力が実績に直結するのでやり甲斐はひとしおです。
村野 そうして理事が丁寧に育てた鶏が、美味しいたまごをつくってくれるのですね。

▲岩島理事のお父様。82歳を迎えた現在も養鶏業に励まれている。
岩島 はい。一般的に、“平飼い”のほうが鶏が感じるストレスが少ないため、たまごは美味しくなると言われています。しかし、実際に食べていただく方々にその違いをお伝えすることはまだまだ難しいでしょう。それに、たまごは生産者の技術によって味が変わるとも言われています。今後は、私たちがどれだけ鶏に愛情を注ぎ、手間暇を掛けて、美味しいたまごづくりに尽力しているかを、いかに伝えられるかが重要になってくるでしょう。やはり、たまごはどれだけ磨いてもたまごですから、見た目は同じたまごでもどんな背景で育てられたかを知っていただけるよう、工夫を凝らしていきたいと思います。
村野 理事のたまごづくりに懸ける想いは、きっと食べる方々の心に届くでしょう。最後になりますが、今後の展望をお聞かせ下さい。
岩島 私共の農場の鶏がどれだけ愛情を込められて育っているかを消費者様に伝えていくと共に、これからも鶏のことを第一義に考えた飼育を続けていきたいと思います。また、82歳になる父が今も手伝ってくれているので、今後もたまごづくりに携わり続けてもらえるよう、そのサポートにも徹していく所存です。

生産者の愛情が たまごの味を左右する

▼一般的に流通しているたまごをつくる鶏は、“ケージ飼い”という小さな籠に鶏を入れる方法で大量に飼育されている。施設はほとんどが自動化されていて、餌やつくられたたまごも全てコンピュータで管理されているという。これに比べ、『栗駒高原』が手掛けている“平飼い”という鶏を放し飼いにして飼育する方法は、飼える鶏の数が少ないだけでなく、様々な面で“ケージ飼い”に比べて生産性が悪い。その分、“平飼い”では1羽1羽を丁寧に育てることができる。岩島理事があえてその飼育方法を選んだ理由はそこにあった。
▼“平飼い”で飼育された鶏がつくるたまごは“ケージ飼い”に比べて美味しいと言われているが、それは生産者の努力の賜物でもある。愛情を込めて鶏を育てることでストレスを感じることなく育った鶏が、美味しいたまごをつくるのだ。養鶏農家が鶏に注いだ愛情の結晶がたまごなのだと言えよう。
「岩島理事のお話からは、いかに鶏に愛情を込めてたまごづくりに臨んでいらっしゃるかが伝わってきました。きっと、そうした情の深さは共に働くお父様から受け継がれたものなのでしょう。これからも、お父様と二人三脚で美味しいたまごづくりを続けられるよう、陰ながらではありますが、応援していますよ!」(村野 武範さん・談)
名 称 |
農事組合法人 栗駒高原 |
|---|---|
住 所 |
宮城県栗原市栗駒深谷日照田146番地 |
代表者名 |
理事 岩島 誠 |
U R L |
|
掲載誌 |
月刊経営情報誌『リーダーズ(LEADERS)』 2016年3月号 |
本記事の内容は、月刊経営情報誌『リーダーズ(LEADERS)』の取材に基づいています。本記事及び掲載企業に関する紹介記事の著作権は国際通信社グループに帰属し、記事、画像等の無断転載を固くお断りします。